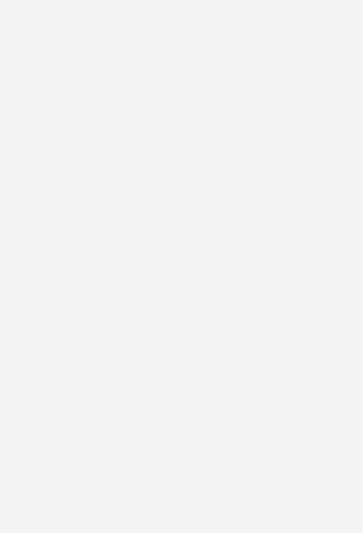書店員向け情報 HELP
出版者情報
書店注文情報
在庫ステータス
取引情報
誰ひとり取り残さない図書館サービス
多様なニーズに寄りそう8つの事例
- 出版社在庫情報
- 在庫あり
- 書店発売日
- 2025年8月7日
- 登録日
- 2025年7月10日
- 最終更新日
- 2025年8月8日
紹介
読書バリアフリーへの関心は高まりつつありますが、まだまだ取り組みとして普及しきってはいません。また、読書バリアフリー法の対象である「視覚障害者等」に含まれない、読書に課題を抱えている人たちがいます。
本書は、実際に読書バリアフリーに取り組んでいる8つの事例を紹介しながら、読書や図書館を取り巻く様々な課題について取り上げています。人々の多様な読書ニーズに寄りそった図書館の環境づくりや対応のあり方を一緒に考えていきましょう。
目次
序章 多様な読書ニーズとそれを支える図書館サービス
序.1 読書バリアフリーへの関心の高まり
序.2 もっと多様な人たちが読書バリアフリーを求めている
序.3 本書の構成と概要
第1章 視覚障害者だけでなく「視覚障害者等」を意識した図書館サービス
1.1 視覚障害者だけでない「視覚障害者等」
1.2 「視覚障害者等」を意識した図書館環境・サービスの現状
コラム 「発達性ディスレクシア」名古屋市志段味図書館での取り組み 名古屋市志段味図書館
第2章 手話と図書館
2.1 言語としての手話
2.2 手話を用いた情報提供・図書館サービス
(1)図書館の取り組み
(2)聴覚障害者情報提供施設の取り組み
コラム 「手話は言語です」 名古屋市守山図書館
コラム 場の共有と同一・同等の情報保障をめざして 堺市立健康福祉プラザ 視覚・聴覚障害者センター
第3章 認知症の人への図書館サービス
3.1 「超高齢社会」を迎えて
3.2 図書館における認知症バリアフリーの推進に向けて
コラム 「認知症の利用者と一緒に取り組む図書館サービスについて」 八王子市教育委員会
コラム 地域の中における認知症バリアフリーに向けた取り組み 川崎市宮前図書館
第4章 外国にルーツのある人への図書館サービス
4.1 外国にルーツのある人の現状
4.2 多文化共生に資する図書館の「多文化サービス」
(1)「多文化サービス」の意義と位置づけ
(2)「多文化サービス」の現状と課題
(3)「多文化サービス」実践上の工夫
コラム 当館で取り組んでいる多文化サービスの実践について 豊島区立図書館
第5章 性的マイノリティと図書館
5.1 国際的な潮流と国内動向
5.2 図書館としての取り組み
第6章 遠方の人にも図書館を身近に
6.1 図書館は誰にとっても身近に存在しているのか
6.2 「アウトリーチサービス」の主なアプローチ
(1)移動図書館
コラム 空とぶ図書館の実践について 沖縄県立図書館
(2)郵送や宅配
(3)電子図書館
第7章 いのちとくらしに直結した図書館
7.1 患者にとっての「患者図書館」の意味
コラム 病院患者図書室の読書文化・環境多様性 千葉県済生会習志野病院
7.2 生活の場としての福祉施設と図書館
第8章 更生と社会復帰を支える図書館
8.1 刑事収容施設の種類と収容者の現状
8.2 刑事収容施設の読書と図書館
(1)法令上の位置づけ
(2)現状と課題
(3)ある刑事施設の事例
終章 まとめと展望
前書きなど
活字の本がそのままの状態では読みづらかったり、現在の図書館などの読書環境では不便を感じたりする人々は決して少なくありません。2019年には「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(いわゆる「読書バリアフリー法」)が制定され、読書環境のバリアフリー化が推進され始めています。
しかし、「読書バリアフリー法」が対象とする「視覚障害者等」の人々だけが、読書のバリアフリーを求めているわけではありません。読書から「誰一人取り残さない」環境づくりを進めるためには、もっと多様なニーズがあることを知り、そこに寄りそった図書館の環境づくりや対応が必要となります。
序.1 読書バリアフリーへの関心の高まり
本書は、筆者が2023年7月に上梓した『読書バリアフリーの世界:大活字本と電子書籍の普及と活用』(以下、前著)の続編です。前著刊行とちょうど同じタイミングで、作家の市川沙央さんが『ハンチバック』(文藝春秋)で第169回芥川龍之介賞を受賞されました。同書では、「目が見えること、本が持てること、ページがめくれること、読書姿勢が保てること、書店へ自由に買いに行けること」という健常性を満たすことを強いる現在の読書環境の問題点を鋭く描き出しています。そして、市川さんは、受賞時の記者会見で、読書バリアフリーが進まないことへのいら立ちが執筆の動機となったと語っています。
市川さんの芥川賞受賞を機に、読書バリアフリーへの関心が急速に高まりました。新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、ウェブメディアなど、さまざまな媒体で、読書バリアフリーが取り上げられるようになりました。
読書に関わる業界団体からも、読書バリアフリーに関する声明やアピールが相次いで出されました。2024年4月には、日本文藝家協会、日本推理作家協会、日本ペンクラブの文芸3団体によって「読書バリアフリーに関する三団体共同声明」が発表されました。また、同年6月には、日本書籍出版協会、日本雑誌協会、デジタル出版者連盟、日本出版者協議会、版元ドットコムの出版関連5団体からも「読書バリアフリーに関する出版5団体共同声明」が発表されています。さらに、同年7月には、図書館問題研究会が「誰ひとり取り残さない図書館をめざします」と題したアピールを第70回全国大会で採択しています。
このうち、「読書バリアフリーに関する三団体共同声明」では、「私たちは表現にたずさわる者として、『読書バリアフリー法』(視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律、2019年6月施行)、改正『障害者差別解消法』(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、2024年4月施行)、『障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法』(障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律、2022年5月施行)に賛同の意を表します。/私たちは出版界、図書館界とも歩調をあわせ読書環境整備施策の推進に協力を惜しみません。」と述べています。また、「読書バリアフリーに関する出版5団体共同声明」では、「『読書すること』に何らかの困難をお持ちの方にとっても、読書があたりまえのものとして、人生とともにあってほしいと思います。読書バリアフリーを実現するための環境づくりや技術の進歩は、出版に携わるすべての関係者の理解と協力の上に進められるものであると考えています。/われわれは、著作者の方々のお考えに寄り添い、その権利が損なわれないように十分に配慮しつつ、あらゆる読者の利便性を高め、長く未来に向けてバリアフリーな環境のもと出版文化をさらに発展させていくための努力を続けてまいります。」としています。
序.2 もっと多様な人たちが読書バリアフリーを求めている
こうしたなかで、前著に対しても、多くの反響がありました。読者からの直筆の感想やメッセージもたくさんいただきました。ありがとうございました。そのなかには、「とても大切なテーマを取り上げて本にまとめてくださったことを心から感謝します。しかし、違和感もあるのです。それは、読書のバリアフリーが必要な人は、外国にルーツのある人など、「視覚障害者等」に限らないからです。この本では、その点への言及が弱いと思いました」といった前著の課題をズバリ指摘してくださるものもありました。
確かに、前著は、2019年に制定された「読書バリアフリー法」が対象とする「視覚障害者等」に重点を置いてまとめています。「視覚障害者等」とは、視覚障害者だけでなく、「発達障害、肢体不自由その他の障害により」、「視覚による表現の認識が困難な者」を指す法律用語です(「読書バリアフリー法」だけでなく、「著作権法」でも同一の定義が用いられています)。海外で用いられる「プリントディスアビリティ」(PD=Print Disability)と重なります。
しかし、「視覚障害者等」に該当しない人たちや「視覚障害者等」であっても「等」に当たる人たちに対する言及が弱かったことは、先の読者の指摘の通りです。「視覚障害者等」に該当しなくても、活字の本がそのままの状態では読みづらかったり、現在の図書館などの読書環境では不便を感じたりする人々は決して少なくありません。例えば、外国にルーツのある人、手話を第一言語としている人、認知症のある人、図書館が近くにないために利用が難しい状態の人、病院に入院しているなど外出がしづらかったりできなかったりする人などなど。読書から「誰一人取り残さない」環境づくりを進めるためには、もっと多様なニーズがあることを知り、そこに寄りそった環境づくりや対応が必要といえます。そこで、前著の続編となる本書を著すこととしました。
序.3 本書の構成と概要
本書は、前著と同様に、専門家向けの専門書ではなく、多くの人たちに読んでもらいたいとの思いで執筆した一般書です。そのため、難しい専門用語や表現は意味が変わらない範囲で、なるべく平易に書き改めました。また、読みやすさを意識して、文字サイズもやや大きめに組んであります。
本書の構成は、次の通りです。
第1章「視覚障害者だけでなく「視覚障害者等」を意識した図書館サービス」では、「視覚障害者等」の「等」に当たる人たちを意識した図書館サービスの意義と現状を解説します。また、具体的な事例として、愛知県名古屋市志段味図書館の実践を紹介します。
第2章「手話と図書館」では、言語としての手話、そして、その手話を生かした図書館と聴覚障害者情報提供施設の取り組みを解説します。そのうえで2つの具体的な事例を紹介します。1つは名古屋市守山図書館と志段味図書館、もう1つは堺市立健康福祉プラザ視覚・聴覚障害者センターの実践です。
第3章「認知症の人への図書館サービス」では、まず、「超高齢社会」の日本の現状と、認知症の人の図書館へのニーズに対応する必要性を解説します。次に、具体的な事例として、東京都八王子市中央図書館と神奈川県川崎市立宮前図書館の2つの実践を紹介します。
第4章「外国にルーツのある人への図書館サービス」では、日本における外国にルーツのある人の現状、その人たちに対する図書館による「多文化サービス」の意義を解説します。そのうえで、具体的な事例として、東京都豊島区立中央図書館の実践を紹介します。
第5章「性的マイノリティと図書館」では、LGBTQなどの性的マイノリティの人たちに配慮した図書館の環境づくりを中心に解説します。
第6章「遠方の人にも図書館を身近に」では、図書館が近くにない地域に住む人たちなどに図書館サービスを届けるアウトリーチの意義と現状を解説します。沖縄県立図書館の「空とぶ図書館」の取組みを具体的な事例として紹介します。
第7章「いのちとくらしに直結した図書館」では、病院患者図書館と福祉施設図書館を取り上げます。病院に入院・通院する人たちにとって、そして福祉施設に入所・通所する人たちにとって、病院や施設に図書館があることはどのような意味を持つのでしょうか。具体的な事例として、千葉県済生会習志野病院患者図書室あおぞらの実践を紹介します。
第8章「更生と社会復帰を支える図書館」では、刑務所図書館を取り上げます。そもそも刑務所に図書館があること自体がほとんど知られていませんが、なぜ図書館(法令では「備付書籍等」といいます)が置かれ、どのような役割を果たしているのでしょうか。
最後に、終章「まとめと展望」では、本書全体のまとめと今後の展望について述べます。
それでは、本書を通して、人々の多様な読書ニーズに寄りそった図書館の環境づくりや対応のあり方を一緒に考えていきましょう。
上記内容は本書刊行時のものです。