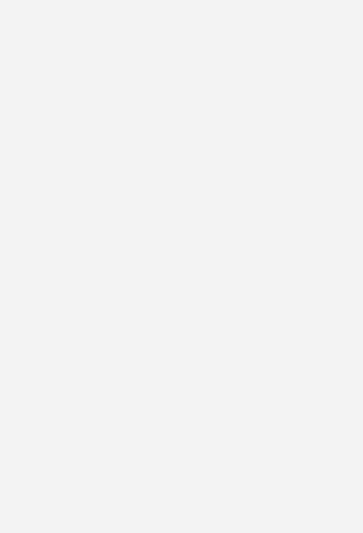書店員向け情報 HELP
出版者情報
書店注文情報
在庫ステータス
取引情報
ヴィゴツキーからドゥルーズを読む
人間精神の生成論
- 出版社在庫情報
- 在庫あり
- 書店発売日
- 2019年3月15日
- 登録日
- 2019年2月13日
- 最終更新日
- 2019年3月14日
紹介
今、改めて注目されているヴィゴツキー。彼は、哲学者ドゥルーズと意外な関係があった。難解で知られるドゥルーズを丹念に読み解き、両者の思考の交差から人間精神の生成と発達、そして目指すべき教育とは何であるかを問うた異色の心理学=哲学の書。
目次
ヴィゴツキーからドゥルーズを読む 目次
はじめに─なぜ、ヴィゴツキーとドゥルーズなのか
1 ヴィゴツキーとドゥルーズの問題圏
2 個別科学と一般科学のあるべき姿
3 本書の章構成
第1章 ヴィゴツキーとドゥルーズ、心の生成論
1 ヴィゴツキーの経験主義批判とドゥルーズの新しい経験論
2 ドゥルーズとヴィゴツキーのシステム論
3 ヴィゴツキー・ドゥルーズのシステム論とジェイムズの「フィアット」
4 人間精神の生成機序とその条件
第2章 学びの本質─ヴィゴツキーとドゥルーズの学習論
1 人間精神の生成と発達の「自己運動」
2 ヴィゴツキーの「学習と発達論」
3 ドゥルーズとヴィゴツキーの学習論
4 発達と学習における模倣
第3章 遊びの世界の本質 81
1 遊びにおける「発達の最近接領域」と意味の生成
2 ドゥルーズの出来事論と〈意味〉、遊び
3 本章のまとめ
第4章 出来事と〈意味〉
1 ホワイトヘッドの「出来事」論と「抱握」、「合生」
2 『意味の論理学』における「出来事」の構造
3 シミュラクル─「反復」とコピーの区別
4 ホワイトヘッドとドゥルーズの「出来事」、そしてヴィゴツキーの「心的体験」
第5章 言語と意味世界の生成
1 言語と意味、ヴィゴツキーとドゥルーズの研究
2 ドゥルーズ─意味の生成論
3 ヴィゴツキーの言葉の意味の生成論と残された問題
4 具体と抽象のはざまで生きる人間
第6章 人間精神の内と外の間にあるもの
1 ヴィゴツキーはベルクソンをどう読んだか
2 ベルクソンの「直観」、「持続」概念とドゥルーズの思想的継承
3 人間の生をめぐるベルクソン、ヴィゴツキー、そしてドゥルーズの議論
4 人を言語の生成に向かわせるもの
第7章 中間世界としての人間精神
1 人間の中の「二重世界」と主体の意味生成
2 概念や知識構造による一元論的説明の疑い
3 人の生の現実─中間世界、あるいは中動態
第8章 生成という時間
1 生成・変化していく時間をみる
2 ヴィゴツキーの微視的発生論とドゥルーズの「ドラマ」
3 人間の生の中で流れている時間
4 新しい構造主義論─生成・変化する構造へ
おわりに 1 生成としての遊び 長橋 聡
おわりに 2 「反復」の復権ということ 佐藤公治
文 献
索 引
装幀=新曜社デザイン室
前書きなど
はじめに ── なぜ、ヴィゴツキーとドゥルーズなのか (一部抜粋)
1 ヴィゴツキーとドゥルーズの問題圏
本書で中心的に取り上げるのは、心理学者のレフ・ヴィゴツキー(Lev Semenovich Vygotsky)と、哲学者のジル・ドゥルーズ(Gilles Deleuze)の人間精神の生成をめぐる研究とその思想である。ここで二人の研究者を論じることに奇異を抱くかもしれない。二人はまったく接点がなく、生きた時代も異なっているからである。ヴィゴツキーは19世紀も終わりに近い1896年にロシアで生まれ、青年時代にロシア革命を経験している。彼は結核の病のために三十七歳という若さで、1934年にこの世を去っている。一方、ドゥルーズはヴィゴツキーよりも一回り若い哲学者である。1925年にフランスで生まれ、1969年から大学の教員として活躍していた頃は、学生の民主化運動にも関わっていた。晩年は呼吸器系の病のために人工肺を使っていたが、1995年に七十歳で自らの命を絶っている。
ここで、なぜ、ヴィゴツキーとドゥルーズなのだろうか?
本書でヴィゴツキーとドゥルーズを取り上げようとしている意図を簡単に述べてみたい。筆者らは主にヴィゴツキーの発達論を教室における相互的な学習や、幼児の遊び活動の場面を中心に論じてきた。その中で、ヴィゴツキーの発達論の中核にあるのは主体の意味生成の活動であるという考えを持つようになった。彼は、人間の精神とその発達は人と人との関わりや社会・文化的なものに支えられながら実現していると主張してきた。同時に、彼は個人の意味生成の過程も重視している。そこでは、社会と個人の間に境界を引くような発想は取らなかった。
それでは、個人はどのような形で意味生成の活動を展開しているのだろうか? それをヴィゴツキーはどこまで明確に主張しているのだろうか? このことに、筆者らは疑問を持つようになった。これはいわばヴィゴツキーの残された問題でもあり、ヴィゴツキー亡き後、残された者たちが取り組むべき課題でもある。そこで、発達研究者ではないが、人間精神の生成の問題を広く論じていたドゥルーズからヒントが得られるのではないかと考えるのである。
ドゥルーズの著作はいずれも難解を極めており、特に心理学を専門にする者にとっては容易に理解できるものではない。だが、彼の主著である『差異と反復』、『意味の論理学』、そして『襞』を筆者らはまさに一行一行読み合わせをするように読み進めていく中で、彼の思想の中心にあるのはまさに人間精神の生成という心理学の重大問題であることに気づいた。その後、筆者らはドゥルーズの他の著作や関連する他の研究者の考えなどにも当たりながら「ヴィゴツキー後」の補完と発展の道を探っていくことを試みたということである。これが本書の背景にある筆者らの問題意識である。
ここで、ヴィゴツキーとドゥルーズをどのように理解していくべきなのか、筆者らの考え方のポイントをまとめてみたい。ヴィゴツキーは心理学者として、人間の精神はいかにして発達していくかという問題に取り組んできた。心理学では伝統的に、精神的活動やその生成を個人の変数とする発想があった。心理学は個人を問題にすることが多いからそれは当然のことだろう。これに対して、ヴィゴツキーとドゥルーズは人間精神の生成と発達を個人という閉じた枠の中で考えるのではなく、個人を取り巻いている外部の存在とその影響の中に位置づけようとした。
ヴィゴツキーの研究の基本姿勢は、歴史・文化的接近、あるいは社会・文化的アプローチと言われるものである。人間の精神的営みや人間意識は自分を取り巻いている外的な環境や社会・文化との関わりの中でしか存在しえないというものである。そこでは、文化的諸変数が具体的な形となって機能している文化的道具の役割も重視されている。人間が有能な存在であることの多くは文化的道具に依存している。だが、ここで注意しておきたいのは、ヴィゴツキーが人間精神の生成的変化を単純に歴史や文化の諸変数に還元するような議論をしていないことである。例えば、『思考と言語』(1934)で扱われている言語について、言語は、はじめは人と人の間の社会的活動=コミュニケーションの手段であったものが、個人の内部へと移し変えられ、個人の思考活動を支えるものとなって、構造や機能を変化させて個人の道具となっていった。そこには、社会・文化的なものが個人の内部へと移し変えられていく過程が論じられている。社会・文化という外にあるものと、個人の精神活動という内にあるものとは複雑に連関し合っている。
ヴィゴツキーが解き明かそうとしたことは、人間の意識の解明であり、意識がどのように生成されていくか、その具体的な生成過程の解明であった。彼はこの心理学の最大の難問を、思考するという活動とそこに密接不可分に関わっている言語活動との絡まりの様相を通して解き明かそうとした。まさに意識がどのように生成されていくかを明らかにしようとした。このことからも、ヴィゴツキーは間違いなく人間精神の生成を論じた心理学者である。
ドゥルーズも人間精神の生成の問題を哲学の視点から論じたが、彼が生成変化を考えていくうえで超えなければならなかったのは、哲学では広く行き渡っていた大陸合理論である。例えば、ルネ・デカルト(René Descartes)に代表されるような、人間には知性や認識が始めから備わっていると考える合理論では人間の精神の生成・変化とその条件を論じていく必要はなかった。しかも神によって人間に理性が与えられていると言ってしまう発想は、人間の手によって人間の精神を変えていく可能性を限りなく狭めるものだった。そこで、ドゥルーズがはじめに手掛けたのは、英国の哲学者、デイヴィッド・ヒューム(David Hume)の経験論を使って人間精神の生成活動を理論化することだった。ドゥルーズの「超越論的経験論」の考えである。『経験論と主体性』(1953)は、ヒュームの経験論を彼独自の視点から読み直したもので、外部世界との関わりの中で得られる経験こそが人間精神の生成の基礎にあるとした。ドゥルーズは人間の経験的活動を積極的に外部と関わっていきながら、その経験を独自に編み直し、システムとして作り上げていく過程として考えようとした。
ドゥルーズの最後の論文となった「内在─ひとつの生 ・・・」(1995)では、外部で起きている出来事を経験として取り込みながら、同時にこの経験を再構成し、自己の意識としてまとめていく「外部-内部の連関」が強調されていた。ここで言う「内在」とは内的意識世界だけを言ったものではなく、具体的な経験そのものに還元されることなく、具体的な経験内容を基礎にしながら経験を新しく意味づけ、解釈していくものであった。いわば従来までの経験論の発想を新しく超えていくという意味で「超越論的経験論」である。
ドゥルーズが静的な構造のシステムとしてではなく、絶えずシステム内部で関係を組み変えていく動的な構造としてシステムを考えた時、そこには生成を生み出していく主体の活動がある。あるいは主体がシステムを構成していく自由である。ここで言う主体性やその自由というのは、決して外部世界から切り離された形の内的なものではない。外部世界と関わり、接触しながらそこから自己の世界を構成していくという主体性と自由である。このように、生きた時代も国も違っているヴィゴツキーとドゥルーズだが、二人には人間精神の生成の問題を解いていくという共通の問題圏があった。
2 個別科学と一般科学のあるべき姿
ヴィゴツキーが本格的な心理学研究を開始した時に著した「心理学の危機の歴史的意味」(1927)では、人間精神の本質に迫るためには心理学はどのような理論と研究方法を取っていくべきかという問題を心理学、さらには哲学、生理学研究まで広く渉猟しながら論じている。この長大な論文で扱われている内容は多岐にわたっており、難解なものだが、ここで彼が主に指摘していることは、これまでの研究では、個別科学が対象にしている具体的な心理事象の問題について、その解明を十分にすることなく抽象的で一般科学の形で理論化してしまう傾向があったということである。本来は個別科学と一般科学とは相互の役割を分担しながら行われるべきで、まずは個別科学の研究成果を蓄積していくことを通して理論構築へ進むという研究展開を目指すべきであった。だが、現実には、研究の趨勢として過剰な一般化、抽象化された理論がまかり通ってしまい、人間精神の真の事象に迫るような一般科学としての理論にはならなかった。
具体的な個別科学と実証的な資料の積み重ねが十分に行われなかったことが招いてしまった問題を、ヴィゴツキーは幾分、難解な形で説明をしているが、ここではその代わりにオリヴァー・サックス(Oliver Sacks)が科学史上で起きたいくつかの出来事を興味深く書いているのを使って考えてみよう。
サックスはヴィゴツキーの研究仲間でもあったルリヤ(Aleksandr Romanovich Luriya)とは生涯にわたって深い親交を結んだ神経科学者であった。彼が「暗点─科学史における忘却と無視」というタイトルで書いたエッセイがある(『消された科学史』(1995)に収められている)。彼は脳科学や神経学の重要な研究としていくつかあったにもかかわらず注目されることなく忘れ去られた研究を取り上げている。その中で心理学にも関係しているものをみてみよう。事故などで四肢の一部を切断せざるを得なくなった人がしばしば持つものに「幻影肢」がある。「ファントム」とも言われているが、既に失った腕や足に痒みを感じたり、これまで存在していた自分の手足から感じるものを失ったという喪失による「疎外感」を抱くものである。「幻影肢」は今やよく知られているものだが、サックスの説明では1864年に神経学者のサイラス・ウィアー・ミッチェル(Silas Weir Mitchell)が「感覚的ゴースト」と名づけて報告書を出していた。だが、この報告書は忘れられ、五十年後に、心理学でも原始反射の一つであるバビンスキー反射で知られている神経学者のジョゼフ・バビンスキー(Joseph Babinski)がこの症状を戦争で四肢を失った人の神経病的トラウマとして1917年に独自に発表している。バビンスキーはミッチェルの報告書があることを知らないで研究をまとめていた。さらに、第二次世界大戦で負傷した兵士たちが受けた同じ症状について、1940年代にロシアのヴィゴツキー派の心理学者のアレクセイ・N・レオンチェフ(Alexei Nikolaevich Leont’ev)とアレクサンドル・ザポロジェツ(Alexander Vladimirovich Zaporozhets)が詳しい内容の研究をまとめている。この時も彼らはバビンスキーの研究を知らないでいた。そして、1960年にこのレオンチェフらの著書の英訳が出て、ようやく広く読者の目にふれられるようになった。これが『手の働きのリハビリテーション(Rehabilitation of hand function)』である。サックスはレオンチェフらを神経学者としているが、正確には心理学者である(もっとも、彼らの研究は心理学の分野だけでなく、生理学や神経学の研究成果を使っているので神経学者という表現になっているのだろう)。だが、レオンチェフとザポロジェツ自身もその後は「幻影肢」についての研究は行っていないし、言及もない。
このようにサックスが重要な問題として取り上げた報告書や研究書が目にふれることなく忘れ去られることが繰り返されたのはなぜなのかということだが、その理由としてサックスは二つのことをあげている。
一つは予想しなかったことや、些細なことには注目しないで済ませてしまうような傾向があったということである。サックスは我々にはお馴染みのゲシュタルト心理学のヴォルフガング・ケーラー(Wolfgang Köhler)が言っていることを取り上げている。ケーラーが1913年に書いた「気づかれなかった感覚と判断の誤りについて」という論文である。ここでケーラーは次のように言う。「科学のどの分野にもそれぞれ、すぐには使えなかったり、いまひとつそぐわないものをほとんど即座にしまい込んでしまう屋根裏部屋のようなものがある。・・・
上記内容は本書刊行時のものです。