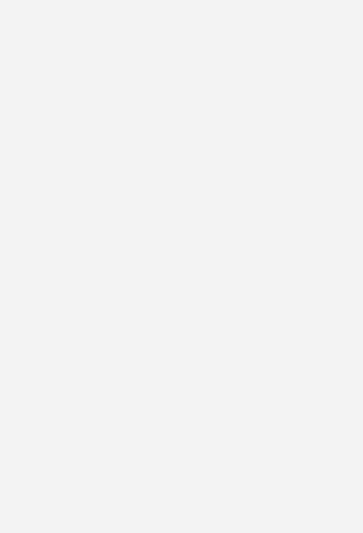書店員向け情報 HELP
出版者情報
在庫ステータス
取引情報
お梅さん
原書: Miss NUME of Japan
- 出版社在庫情報
- 在庫あり
- 初版年月日
- 2011年6月
- 書店発売日
- 2011年6月27日
- 登録日
- 2011年6月1日
- 最終更新日
- 2011年6月27日
紹介
(あらすじ)
日本人青年高島織人は、許嫁のお梅を日本に残しアメリカ留学へ旅立つ。8年後、帰国する船中で彼はアメリカ人女性クレオと猛烈な恋に落ちた。しかし彼女にはすでにフィアンセがいたのである……
一方、8年ぶりに織人と再会したお梅には、彼に対するかつてほどの愛情はなかった。そのとき、織人が恋したアメリカ人女性のフィアンセ、シンクレアと出会うことになる。それこそが、この4人の苦悩と悲劇、そして幸福のはじまりだった。
前書きなど
あとがき
1
明治36年(1903年)、永井荷風はアメリカに渡った。
ほとんど四年におよぶアメリカ滞在中に、荷風はフランス語の習得のために、ゾラ、ピエール・ロティ、モーパッサン、ミュッセ、ユイスマンスなど、多数のフランス小説を読みつづけていた。「自分はアメリカの文学については此れまで何一つ注意を払った事がない」(「市俄古の二日」)と書いている。その荷風が「西遊日誌抄」の明治37年2月26日の項に、「米國近刊の小説The Heart of Hyacinth(お蘭の心)を一読す。閨秀作家オノトワタンナの著す處、日本の松島を舞台として英國の孤女を描ける可憐の恋愛小説なり。さして傑作といふにはあらねど文章清楚にして情趣まゝ掬すべきものあり。日本を舞台とし日本の風俗を描きたる点に於て余は過半の好奇心をもて愉快に二百余頁を一日にして読み終へたり。」と書いている。
私は戦後にこれを読んで、はじめてオノト・ワタンナという「閨秀作家」の存在を知ったが、なにせはるかな過去の、それも二流作家の作品なのでまったく読む機会がなかった。以来、いつの日にかこの作家を読みたいと念願してきたのだった。翻訳家としての私は、アリス・ガーステンバーグ、アナイス・ニン、カースン・マッカラーズ、アーシュラ・ヒージなど、すぐれた女流作家を紹介、翻訳してきたが、オノト・ワタンナについては、まったく紹介する機会がなかった。
このたび、はからずもオノト・ワタンナを翻訳する機会を得たことは、少年時代の宿願の一つを果したわけで、私としてはうれしいかぎりである。まず、この作家の存在を教えてくれた荷風に感謝しなければならない。
この翻訳とは関係がないが―武田勝彦先生が「荷風閲読の西欧文学」というエッセイを発表なさった。(「公評」2011年3月号)このエッセイは―「荷風のアメリカ文学観賞はどのように行われたのか」というテーマをもっている。
荷風とアメリカ浪漫主義文学との出会いが明瞭な例は、女流作家「渡名おのと」Onoto Watanna―本名、ウィニフレッド・バブコック・イートン―Winnifred Babcock Eaton ―だ。(中略)「渡名おのと」は国籍はカナダ。生まれは荷風と同じ一八七九年(明治一二年)。所は長崎。父は富裕な貿易商で、当時中国、日本と取引をしていた。渡名が何歳まで日本にいたのか、どこにいたのかは今のところ明瞭ではない。彼女の創作物から判断すると、東京、横浜、仙台、福井、京都に詳しいので、これらの都市に旅したのではないかと思われる。一八九三年(一四歳)に、彼女の処女作がモントリオールの雑誌「メトロポリタン・マガジーン」にのっている。したがって、少なくともその頃までに日本を引き上げていたと見るべきであろう。渡名の父は、日本からニューヨークのウォール街に居を移した。その後、商売に失敗し、モントリオール、トロントと転々とした。渡名もこれらの地で、在日日本でいう中学・高校を終えた。彼女は一八九五年には、シカゴの「コンキーズ・マガジーン」に日本を背景とした「人力車」を連載している。このほか、彼女の文筆活動は華やかであった。米英両国の一流出版社から、つぎつぎ豪華な単行本を出版した。
これがオノト・ワタンナの経歴に関して最近書かれた記述であるが、『お梅さん』の読者のために、訳者としてもう少し詳しく述べておく。
オノト・ワタンナは、1875年8月21日、カナダ、ケベック州モンレアル(モントリオール)に生まれた。本名、ウィニフレッド・イートン。
父のエドワードは、イギリスの貿易商で、19世紀後半に、清国、上海で、おもに機械類をあつかっていた。日本とのかかわりは、おなじイギリス人の貿易商で、神戸在住のジョージ・ホジキンスンとの取引によると考えられる。
当時、清国はロシアと紛争を起したが、イギリスのゴードン将軍が仲介し、ようやく危難をまぬかれた。光緒帝はドイツの設計で、旅順砲台を築き、朝鮮の危機にそなえたが、一方、ヴェトナムに侵攻したフランス軍に敗れ、フランスがヴェトナムを保護国とするような危機にさらされていた。この時期の清国は急速な工業化をめざしていただけに、エドワードのビジネスも成功した。
エドワードは上海で、清国人の女性と親しくなる。英語名はグレイス。イギリス人宣教師の養女として育てられた美少女だった。華名は、ロータス・ブロッサムという意味だったという。おそらく、蓮花とか金蓮といった名前だったと思われる。
1870年代の初期、イートン一家は清国から引き揚げ、ニューヨーク、ハドソンに移住した。(イギリスが清国に対して、租界の開設、拡大を要求するのは、1889年からで、阿片戦争で奪った香港に隣接する九龍に租界をひらく。つづいて、威海衛を租借地とする。エドワードが貿易商として動いていたのは、それよりずっと前で、清国の排英、排外運動がまだ激化しない時期だった。)
イートン一家のニューヨーク滞在は短く、しばらくしてカナダに移住した。
1875年、オノト・ワタンナが生まれた。(したがって、永井荷風より年長ということになる。)オノトが清国に滞在していたとか、日本で生まれたという説は、にわかに信じがたい。イートン夫妻は14人の子どもがつぎつぎに生まれたため、一家のカナダでの生活は楽ではなかったと思われる。
十歳年上の姉、イーディス・モード・イートン(1865~1914年)は、早くからジャーナリズムの世界をめざして、「シン・シンファ」というペンネームで、「レディズ・ホーム・ジャーナル」などにエッセイを発表していた。オノトが作家をめざしたのは、おそらくイーディスの影響による。
貧しい家庭から脱出しようとしていた少女を想像してみよう。オノトは、17歳で独立しようとする。しかし、当時のアメリカの女性差別、きびしい家父長制の仕組みのなかで、ろくに学歴もない少女が就職できる可能性はきわめて低かった。オノトは、わずかな手づるを頼って、ジャマイカ、キングストンに行く。当時は英領で、コーヒー、ココア、バナナなどの輸出がジャマイカ経済をささえている最貧国であった。この時期、インド系、清国系移民が、数千名の規模で移住していたという。オノトは家計を助けるために、貿易会社の速記者、秘書として働いた。
オノトは、やがてシカゴに移った。当時のシカゴは、のちに「シカゴ派」と呼ばれる作家、詩人、評論家たちが集まりはじめていた。世紀末の大きく変化しようとする社会情勢のなかで、オノトは短篇の習作を書きはじめる。従来の文学史的記述においては、まったく無視されている存在に過ぎないが、オノトが作家として登場するのは、まさにこうした時代であった。
2
永井荷風の伝記を書いた秋庭太郎の記述によれば、オノトの本名は―ウィニフレッド・イートン・バブコック・リードという。バブコックは初婚、リードは再婚した夫の姓という。
二十代のウィニフレッドの写真が残されている。いくらかきつい表情で、理知的な美貌だが、やはり白人種というよりも東洋人、とくに日本女性を思わせる美少女だった。その写真に、墨痕あざやかに、渡名おのとという署名があった。
中国系カナダ人女性が、なぜ日本名(と本人が考える)「ワタンナ」をペンネームに選んだのか。
日本人の常識では「ワタンナ」という姓は、まず考えられない。渡名の中国読みは、Du Ming で、ウィニフレッドは、渡が、わたる、わたす、(時間を)過ごす、やり過ごす、(難関を)きりぬける、くぐりぬける、といった意味があることを知っていたと思われる。「ワタナベ」の省略形で「ワタンナ」を選んだというのも、ちょっと考えにくい。(ただし、「ワタナベ」がオノトにとって重要な命名であることは、『お梅さん』の姓であることから想像できる。)
これをペンネームとして選んだのは―もとより重要な意味がある。名を渡るというのは、おのれのアイデンティティーを変えることにほかならない。母が蓮として「静客」を意味したように、「お梅さん」は「清客」を意味し、「お蘭」が「幽客」を意味したはずである。「オノト」は、自分がイギリス人と清国人の混血ではなく、日本人として「変装」することが、いわば新たな自己主張、偏見や束縛、不平等からの解放という願望として生じたということではないか。この「渡名」には、若いアジア人の女性としての、いじらしい、切ない願望がこめられていた。その背後には、当時のアメリカにおける、アジア人、とくに清国人排斥、人種差別という現実があったと考えてよい。あえていえば、オノトが名号を変えたのは当時のアメリカに対する反措定だと思ってよい。
「オノト」については不明だが、「タカシマ・オリト」の命名を考えれば、おなじ音韻をもつ(と、ウィニフレッドが考えた)単語と想像がつく。「オリト」は東洋人の連想であり、「オノト」は、おそらく地名の「能登」の連想による。私は「オーミ」を「近江」としたが、これもおなじ推量による。
『お梅さん』の名はNumeだが、作者は在米日本人の発音で「オンメさん」と聞いたのではないか、と考える。
3
永井荷風はオノトの『お蘭の心』を目して、「さして傑作といふにはあらねど、文章清楚にして情趣まゝ掬すべきものあり」と称したが、『お梅さん』を読んだかどうか、これは判然としない。
私としては、『お梅さん』を読んだ、もうひとりの文人にふれないわけにはいかない。ヨネ・ノグチ(彫刻家イサム・ノグチの父)である。
野口米次郎は、明治26年(1893年)、19歳にして渡米した。サン・フランシスコに到着したが、英語もろくにしゃべれなかった若者の生活は辛酸をきわめた。しかし、若い米次郎は、アメリカの生活に適応してサン・フランシスコを中心に無銭旅行をつづけた。
1896年、ヨセミテ渓谷を徒歩で踏破したが、このときの印象が「渓谷の声」The Voice of the Valley という詩になった。
やがて、最初の詩集『明界と幽界』Seen and Unseenが出版され、詩人、ヨネ・ノグチは一部に知られることになる。
ヨネ・ノグチが、いつ、どこでオノト・ワタンナと知りあったのか。オノトの研究家、ダイアナ・バーチョルの証言によれば、オノトはノグチに『お梅さん』を献呈したという。処女作といってよい『お梅さん』を執筆中だったオノトが、まだ無名の若い東洋人、それも詩人を志していたヨネ・ノグチに大きな関心を寄せたことは想像にかたくない。オノトの作品に見られる「日本理解」が、当時のアメリカ人の日本理解をはるかに越えていたことに―私はヨネ・ノグチの助言を想像する。『お梅さん』でオノトが柿本人麿や大伴家持などに言及していることは、後年(1924年)、オクスフォードで行われたヨネ・ノグチの講演、「日本詩歌の精神」を想起させる。そして、富士、湘南、松島などへの言及も、たんなる観光案内ではなく、日本をより一層深く理解しようとしたオノトの姿勢と、おそらくヨネ・ノグチの熱心な助言の結果と見てよいのではないだろうか。
ヨネ・ノグチは、やがてシカゴを経由、ニューヨークに出た。そして、『日本娘のアメリカ日記』を書く。これが好評だったので、翌年、『日本メイドのアメリカ手紙集』を書く。イギリス滞在の費用を得るためだった。
ヨネ・ノグチが『日本娘のアメリカ日記』といった、いかにもアメリカ人の好尚に投じた際ものを書いた動機は、オノト・ワタンナの作品を読んで、アメリカにおけるジャポニズム、ないしは、日本文化に対する潜在的な関心を知ったからではなかったか。
荷風が心を動かされた『お蘭の心』が出た1902年、ヨネ・ノグチはアメリカを去った。彼が自費出版した詩集『東方より』は、イギリス詩壇に大きな反響を喚ぶ。当時の大作家、トマス・ハーディー、批評家、アーサー・シモンズの賞讃を得て、ヨネ・ノグチは東洋を代表する詩人と目されるに到った。
おなじ1902年、オノトにも大きな成功がやってくる。
『日本の鶯』A Japanese Nightingale(1901年)が注目を集めた。この作品はただちに劇化され、ブロードウェイでヒットした。主演は、ブロードウェイきっての「娘役」、マーガレット・イリントン。ブロードウェイのヒットによって、ロンドンではただちにオペラ化され、ソプラノのメアリ・テンペストが主役の「お雪」を演じた。メアリ・テンペストは、メルバ、ガリ=クルチ、トティ・ダルモンテ、オペレッタのフリッツィ・シェッフなどと同時代のソプラノだが、1915年にサイレント映画の『ブラム夫人のプディング』に主演している。
プッチーニのオペラ『蝶々夫人』のスカラ座初演が1904年2月だったことを想起すれば、この時期、『ミカド』、『白墨の輪』、『日本の鶯』、『蝶々夫人』とつづく流れから、日本、ひいては東洋に対する関心が高まっていたことが想像できる。
『日本の鶯』は非常な成功をおさめ、映画化されている。ジョージ・フィッツモーリス監督、主演はファニー・ワード、ウィリアム・ローレンス。ついでにふれておけば、この映画に、日本人、徳永フランクが出演している。後年、帰国し、カメラマンとして草創期の日本映画史に名を残している。
4
作家、オノト・ワタンナは、その後、着実に長篇を書きつづける。
『お蘭の心』(1902年)、『二条の娘』(1904年)、『日本爛漫記』(1906年)、『お珠さん』(1910年)と「日本小説」を書きつづけた。これ以後の長篇として知られているのは『家畜』(1922年)、『王様のペン』(1925年)あたりまでだろう。
ただし、オノトは、姉のイーディスの不幸な死のあとで、それまでと違った分野に進出している。当時、映画で成功したシナリオ作家としては、アニタ・ルースやエリナー・グリーンなど、女性ながら一流の作家が多かった。映画人としてのオノトは、1924年から30年代前半にかけて、『ショーボート』、『シャンハイ・レイディー』、『ミシシッピー・ギャンブラー』、『オペラ座の怪人』などのシナリオを担当した。いずれも後年トーキーでリメイクされているから、その内容は私たちにもよく知られている。
オノトがシナリオでは日本趣味ではなく、スケールの大きなスペキュタクラーな作品を手がけていることもおもしろい。自分の文学と、映画は別ものと割り切っていたのだろうか。
その後のオノトは、ニューヨーク在住の頃に、結婚して、息子三人、娘一人を得た。しかし、初婚の夫と別れて1917年、フランク・リーヴスと再婚。カナダに戻った。つまり、ハリウッドから去ったのである。
カナダでは、小劇場運動に尽力し、「リトル・シアター」を主宰している。小説を書きつづけていたかどうか。戦後、カナダ作家協会のカルガリー支部長になった。
1954年、オノトはカリフォーニアに旅行したが、バットという土地で心臓発作を起して急逝した。享年、78歳。
『お梅さん』は、オノト・ワタンナが初めて世に問うた長篇、短い長篇に過ぎないが、いろいろな読みかたができるだろう。
アメリカの「浪漫主義文学」などと見るよりも、はっきりロマンス小説と見たほうがいいだろうし、世紀末小説と見ることもできよう。ただし、私たちが漠然と考える爛熟と退廃に沈湎する「世紀末」ではなく、19世紀に考えられた「世紀末」―つまり、再生への意欲を秘めた「世紀末小説」と。
このことは、『お梅さん』が、中国系の少女によるジャポニズムの作品だっただけに、その後のオノトの世界とどのような脈絡をもって関連し、またその後のアメリカ批判、さらには対日批判としてどう展開していったのか、というおもしろい問題につながる。少し注意すれば―オノトより早く、ジャポネズリの先駆的な作品となったピエール・ロティの『お菊さん』に対する婉曲な否定、日本女性に対するあらたな評価が書き込まれていることに気がつく。
あるいは、19世紀にようやくジャンルとして成立した「大衆小説」のなかの「恋愛小説」―それまでのダイム・ノヴェルと違って、作品全体の色調や気分から、わかわかしいアメリカの少女のファンタジーがあえかな哀愁の美しさを漂わせている作品と見るか。はたまた、おのが信条に身をかけて、それがかなわぬとき、みずからのいのちを絶つことを辞さない日本人の壮烈な美意識に、この作品の愛しさを見るか。観光案内にして一編の小説なのか、一編の小説にしてついに観光案内に過ぎないのか。すなわち、オノトは「日本小説」で何を書こうと企て、どこまでそれを実現できたのか。
オノト・ワタンナは、自分では意識しなかったにせよ、封建的なモラルや規範をうち破り、異国人との愛という困難な状況のなかに飛び立とうとする新しい女性を描こうとした、と私は見る。
そしてまた、この作品を、アメリカ小説にまだ萌芽としてもその姿を見せていない、20年代のフラッパーたち、フラートの先駆的な作品としても読むことができるだろう。『お梅さん』からさほど遠くない時代と場所に、やがてクララ・ボウやビーブ・ダニエルズ、コリーン・ムーアたちが登場する。
『お梅さん』の翻訳について書いておきたい。
ある日、私は新進の劇作家として知られる垣花理恵子さんと話をしていた。いろいろな話題が出たが、日本語の大きな変化を話しあっているうちに、たまたま若き日の永井荷風が読んだアメリカの女流作家、オノト・ワタンナの話題になった。私が、なかば冗談のように、はるかな昔の明治時代の文学作品を翻訳(というよりパスティッシュ、ないしはパロディー)してみたらおもしろいでしょう、と話すと、垣花さんはにわかに興味をもって、私がやってみたらどうかとすすめてくれた。
私が『お梅さん』を翻訳する気になったのは、ひとえに垣花さんのおかげである。そして、この出版を承知してくださった「柏艪舎」の山本光伸さんに心から感謝申しあげる。垣花さんは、私の原稿によく眼を通して、その都度、適切なアドヴァイスをあたえてくださった。編集にあたられて、いつも適切な注意をあたえていただいた熊木信太郎さん、この翻訳に協力してくださった川口康子、鬼頭玲子、土谷幸恵、水野恵のみなさんに心から御礼申しあげたい。みなさんのお力添えがなかったら、この『お梅さん』は成立し得なかったと思われる。私としては感謝のことばもない。
日本語の大きな変化は、幕末期から明治にかけて欧文脈(翻訳語)が、私たちの文章に導入されてからで、これが日本語の急速な変化の要因になっている。私が『お梅さん』の翻訳で、あえて古色蒼然たる措辞を用いたのも、もとより成算あってのことであった。この翻訳で、私は悲運といわずあえて非運という。なぜなら悲しい運命と非想天の運命とはおのずから違うからである。非業の運命、あるいは運命の不條理を言外にほのめかすための非據の試みといおうか。この翻訳を終えたあと、東日本大震災という未曾有の非運を経験したときも―私は心に深く期するところがあって、非運ということばを選ぶ。そして、私は、いまの日本語に欠けているものを表現することによっておのれの翻訳の価値が生じると思っている。日本語が失ったものについて、私がはっきりした知識をもっている最後の世代だからだろうか。私たちの失ったものはけっしてわずかなものではない。だから、私は自分に欠けたものをアメリカの一少女の作品をつうじてあらためて見つめようと試みたに過ぎない。
最後に―この本の装幀を引きうけてくれた吉永珠子に感謝する。私が女子美のキャンパスで教えていた頃、彼女は「芸術学部」の助手だった。私の周囲には、岸本佐知子、田栗美奈子、堤理華、立石光子、作家の山口路子、森茂里、詩人の野木京子など多数の才女たちが集まっていたが、そのなかで吉永珠子は、TVの作曲をしたり、いろいろな分野で活動して異彩を放っていた。その彼女が私のために装幀を引きうけてくれたのだから、うれしいことであった。いつかオノト・ワタンナの作品、『お珠さん』を訳す機会があったら、ぜひ珠子ちゃんに装幀をお願いしようと思っていたので。
中田 耕治
2011年5月
上記内容は本書刊行時のものです。