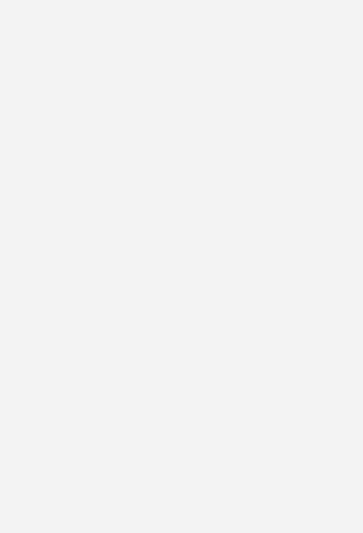書店員向け情報 HELP
酒蔵最前線 日本酒、米づくりから始める
- 初版年月日
- 2018年9月
- 書店発売日
- 2018年9月14日
- 登録日
- 2018年8月10日
- 最終更新日
- 2018年9月20日
紹介
酒蔵が自ら米を作る時代がきている。米の旨みを目いっぱい引き出す日本酒造りをめざす酒蔵が徐々に増えてきた。まさに酒蔵の未来を指し示す羅針盤ではないか!
本書では米作りから酒造りを始めた先駆的な酒蔵6蔵の取組を紹介する。
目次
はじめに
第1部 日本酒事始
1 日本酒の製造工程
2 日本酒の歴史
3 酒米
4 主な酒米
第2部 自耕自醸蔵
1 地元農家と歩む「栽培醸造蔵」
泉橋酒造(神奈川県海老名市下今泉)
2 「自耕自醸」の“農家宣言”蔵
浜嶋酒造(大分県豊後大野市緒方町下自在)
3 新しい時代を切り拓く酒
(株)せんきん(栃木県さくら市馬場)
4 里山が生み出す“一貫造り”
秋鹿酒造(大阪府豊能郡能勢町倉垣)
5 那須の大地が育む「大那」ブランド
菊の里酒造(栃木県大田原市)
6 根知谷が育む米と酒
渡辺酒造店(根知男山)(新潟県糸魚川市根小屋)
参考文献
おわりに
6蔵の酒を買える店・飲める店
前書きなど
はじめに
◆食事と楽しむ日本酒
日本酒を洋風の居酒屋感覚で提供する店が増えている。日本酒に合わせる料理も和食系、洋食系、エスニック系と幅広い。英語の「バー(bar、酒場)」をフランス語やスペイン語風に「バル」と発音し、「日本酒バル」を名乗る店も多い。
その店の日本酒メニューは純米酒を中心に、どちらかというと小規模または中堅クラスの酒蔵のものが多い。しかも流通業者が勧める日本酒を言うがまま置いているのではない。店主が直接、全国の酒蔵を訪問したり、日本酒イベントに参加したりして、好みの日本酒を見つけてくるケースが目立っている。
かつて“吟醸酒ブーム”とか“辛口淡麗ブーム”といわれた時期があったが、日本酒バルはそうした一時のブームとは無縁だ。全国新酒鑑評会の金賞受賞酒を前面に出すこともない。酒米や酵母の種類、精米歩合、日本酒度、山廃酛・生酛造り、風味・味わいなど多種多様で酒質設計の確かな日本酒を置いているのが特徴だ。
日本酒の提供の仕方も良い。食事との相性を考え、純米酒、吟醸酒、山廃、生酛と客の好みに合わせて提案してくれる。山廃や生酛だと、ぬる燗を勧めてくれる。その酒の個性や酒質に応じて冷酒、常温、熱燗を選んでくれる場合もある。
何より、店員が日本酒のことをよく勉強している。それに客とのコミュニケーションを大切にしている。彼らとの会話にうれしくなり、ついもう一杯と盃に手が出てしまう。
鑑評会の場合は、酒蔵の酒造技術を競うコンクールの意味合いが強い。出品酒は、“酒米の王様”といわれる山田錦と吟醸酵母を使い、特別に中汲み・袋吊り・斗瓶囲いで醸した特別仕様の酒だ。蔵人が手塩にかけて造った酒だが、審査員が少量を口に含む以外、市場に出回らないので消費者が飲む機会はない。
造り手優先の技術コンクールなので採点で料理とのペアリングが評価されることはない。ペアリングとは、料理(食材)と酒との相性の良い組み合わせのことをいう。「マリアージュ(料理とワインの相性)」同様、元々、ワイン用語だったが、日本酒の世界でも使われるようになった。その年の新酒が対象なので熟成酒は除外される。江戸時代には「秋上がり」「冷やおろし」という言葉があった。その年の春までに搾った酒は暑い夏を越して涼やかな風が吹き始める秋に飲むのが良いとされたのだ。
鑑評会は、極端に言えば飲み手不在のコンクールだ。このように、長年、酒造りの技術のみが尊重されてきた背景には、並行複発酵という日本酒の特異な製造技術があった。これは米に含まれるデンプンを麹の力で糖に変える「糖化」と、糖を酵母の力でアルコールに変える「発酵」の過程を同時に行う日本酒の伝統技法である。ワインの場合、原料のブドウに糖分が含まれているから「糖化」の過程が必要ないので「単発酵」といわれる。
同じ醸造酒でも、単発酵で造られるビールやワインはアルコール度数が5~10数パーセントと低めだ。ところが「並行複発酵」で造られる日本酒はアルコール度数が18~19パーセントまで上がる。原料米を最後の最後まで発酵させてアルコール度数を高めることができるからだ。
技術に依存してアルコール度数を上げれば上げるほど、酒質はすっきりとした辛口になる。原料米の特性や風味がほとんど失われてしまうからだ。そこに吟醸系酵母を使って華やかな香りを発散させた“厚化粧”の大吟醸酒が主に鑑評会で金賞を取っている。
現在、飲み手が求めている日本酒はこういう酒ではない。むしろ、多種多様な食事と一緒に楽しんで飲める多種多様な酒ではないか。
鑑評会で金賞を取る酒より、飲み手が食事と一緒に楽しめる酒を理想とする酒蔵が増えているのは確かだ。日本酒バルは間違いなく、20代、30代の若者や女性の支持を得ている。
◆地元農家との“協働”
こうした飲み手の意識の変化が造り手の意識も変え始めている。鑑評会で金賞を取る酒ではなく、飲み手が求めている酒をめざす造り手が増えているのだ。
戦後の米不足の時代に醸造用アルコールを大量に添加した三増酒が生まれ、高度経済成長期には三増酒や普通酒が当たり前に市場に出回った。三増酒とは第二次大戦後の米不足の時代に導入された日本酒の製造方法で、三倍増醸酒の略。米と麹で造った醪に醸造アルコールを加え、さらに水あめやブドウ糖など糖類を添加して、三倍に増量した酒のことだ。だが、オイルショックなどで経済が低迷する中、日本酒の消費量は減少し続け、全国の小規模な酒蔵は次々と姿を消していった。
本書にも登場するが、普通酒を大手酒蔵へ桶売り(酒蔵間で原酒を桶に入れたまま売買する取引のこと。未納税取引ともいう)していたためかろうじて生き残った蔵もあった。だがそうした蔵は、大手酒蔵が取引を停止すれば一気に倒産するしかない。風前の灯火といってもいい状態だった。
本書に登場する「大那」や「仙禽」の酒蔵もやはり、先代が桶売りのため酒質の悪い「普通酒」を造っていた。ラベルに自分の蔵の名前の出ない桶売りであっても、生産高は1000石や2000石はあった。食うには困らなかった。
だが、そんな酒を造っていても「将来はない」と判断した若き蔵元たちが英断を持って大鉈を振るった。「売れればいいだけの酒」から「自分が飲みたい酒」へと大きくハンドルを切ったのだ。
それは時にはタンク数本分、数十石の純米酒造りからのスタートだった。これが売れなければ倒産は間違いない。その際、共通しているのは、酒造工程を昔ながらの手造りに戻すことと、原料米へのこだわりだ。
多くの酒蔵は米をよそから仕入れて醸造するのが当たり前だ。良質な山田錦や雄町を求めて奔走する蔵も数多い。
反対に、「未来の日本酒」を志向した若き蔵元たちは、地元の栽培農家に着目した。質の良い米を作っている地元農家と契約することで、酒米の質の確保と安定供給が実現できるからだ。
地元農家は必要な酒米の質と量を念頭に酒蔵と意見交換しながら生産計画を立てる。酒蔵の方はその年の米の性質を知り尽くしたうえで酒造りに当たる。酒造工程の中でも米の善し悪しが分かるので、酒造りが終わった後、翌年の米作りをめぐって農家に稲作の改善を求めることができる。
こうした酒蔵と農家の“協働作業”によって、酒蔵は酒造りのモチベーションをさらに上げているという。
一方、自社田や自家栽培田を確保して自分たちで米を作りはじめた酒蔵もある。本書で取り上げた「泉橋」「秋鹿」「根知男山」「鷹来屋」がそれだ。春から秋までは米を作り、秋から翌春までは酒を造る。蔵元自身がトラクターを運転し、苗床作りから、田植え、草取り、刈り入れまでを行っている蔵もある。
酒蔵と米づくりが一体となった新しいスタイルの酒造りは、「農醸一貫」(秋鹿)、「栽培醸造蔵」(泉橋)、「自耕自醸」(鷹来屋)といった新しい呼び名を生み出した。本書では鷹来屋の蔵元のご好意で「自耕自醸」を使わせてもらっている。いずれも原料の米から責任を持って酒を造るという姿勢は共通している。その点では地元農家との“協働”で米作りにまい進する酒蔵も同じだ。
米作りを酒造りの出発点に置いた酒蔵の場合、無農薬や減農薬、有機農業への視点を忘れることができない。
「秋鹿」では無農薬のみならず、赤糠と籾殻を発酵させた堆肥を利用するなど酒蔵ならではの循環型農業を実現している。
「仙禽」は地元の有機栽培農家と契約している。そこでは従来の稲作と違って、肥料も農薬も使わず、除草もせず、米の持つ本来の生命力と生態系を十分に生かした栽培方法が取られている。
米作りと酒造りには水が欠かせない。特に日本酒成分の約80パーセントは水だ。仕込み水が酒質に直接、影響を与えるのは当然だ。
昔から酒蔵は良質の水が湧出する土地に建てられた。「硬水」で知られる兵庫・灘の「宮水」はリン、カリウム、カルシウムなどミネラル分を多量に含んでおり、酵母の働きを活発化し、強くて安定したアルコール発酵を促進する。
「軟水」も負けてはいない。「軟水」の場合、発酵がゆるやかに進むので、軽くて柔らかく、すっきりした味わいの酒になる。軟水仕込みは安芸津杜氏が確立したといわれるが、発酵が停滞しやすいので高度な技術が必要とされる。
本書で取り上げたどの蔵も米作りと酒造りに同じ水脈の水を使っている。しかも「秋鹿」「仙禽」「鷹来屋」「根知男山」などほとんどの蔵の水は「軟水」だ。「硬水」だとアルコール発酵が力強く進むので米の旨みが出にくいのかもしれない。
いずれにせよ米と水を重視した酒造りこそが、「自耕自醸」の大きな特徴なのだ。
◆未来を切り拓く米作り
実は、こうした原料から醸造まで一貫して行う酒造りは、フランスのワイン醸造の世界ではごく普通に行われてきた。
世界的なワイン銘醸地として知られるブルゴーニュ地方では、醸造家はみなブドウ栽培の農家でもある。個人や兄弟で経営する小規模な蔵が多く、ブドウ栽培からワイン醸造まで一貫して行う生産者はドメーヌ(区画、畑)と呼ばれる。
フランスのもう一つのワイン銘醸地ボルドー地方では巨大な醸造メーカーが建ち並び、シャトー(城)と呼ばれているのとは対称的だ。
酒造りを米作りから始めた蔵のいくつかが、ボルドーではなく、ブルゴーニュの生産者をモデルにしたというのも理解できる。実のところ、「泉橋」や「鷹来屋」の蔵元は、醸造家として「農の心」を学びにブルゴーニュへ視察旅行に出かけている。
ブルゴーニュのコート・ドール(黄金の丘)には、かの有名なロマネ・コンティやモンラシェ、ムルソーなど世界最高級ワインのブドウ畑が集まる。年中、観光ツアー客でにぎわうほか、秋のヴァンダンジュ(収穫)の季節になると全国から学生ら若者が押し寄せ、短期アルバイトに汗を流す姿が見られる。
だが、コート・ドールの畑は貝殻だらけの石灰質で乾燥しザラザラしている。雨が降っても水はあっと言う間にきれいさっぱり消えてしまう。ブドウがパレスチナ原産というのも頷ける。湿潤な日本の田んぼとは大きな違いがある。
そのうえ、ワイン醸造では、ブドウ自体が糖分を含んでいるのでブドウを潰して果汁にし、酵母を加えれば発酵が進む。米に含まれるデンプン質を麹菌の力で糖分に変え、それを酵母によって発酵させるという、日本酒の並行複発酵とは雲泥の差がある。
ワインではブドウ畑の立地するテロワール(気象・土壌など自然条件)が重要になる。南向き斜面であるコート・ドールのような最高のテロワールのブドウ畑を所有することが最高のワイン造りの必要条件といえる。ワインの質はブドウに大きく依存していることになる。
だが、日本酒ではいかに良い米を使っても造りを失敗すれば良い日本酒にはならない。原料の善し悪しと技術の善し悪しが共に必要になるのが「並行複発酵」で造られる日本酒の特性といえる。ブルゴーニュに出かけた蔵元たちの多くは、最初、「日本酒ドメーヌ」を意識したというが、日本酒とワイン醸造の違いに気づき、「日本酒は日本語で語るべきだ」と考えるに至った。「栽培醸造蔵」や「自耕自醸」といった言葉はその結果として生み出された。
ではなぜ酒蔵が米を作るのか? 米はブドウと同様に自然の恵みだ。その自然の恵みをおろそかに扱うことなく、米の旨みを目いっぱい引き出す酒造りをめざしているからだ。
本書では第1部で日本酒の製造工程や酒米など基本事柄について解説し、第2部では、米作りから酒造りを始めた先駆的な酒蔵6蔵を紹介する。
自社田や自家栽培田を持って自ら田んぼを耕す蔵、地元の栽培農家と契約し“協働”で米を作る蔵、中には食とのペアリングを重視し6次化産業に取り組む蔵もある。
こうした“未来派”ともいえる酒蔵の生産スタイルが、近い将来、日本酒業界の常識となり、一時のブームに終わることのない、新しい日本酒の時代を切り拓くのは間違いない。本書がその先駆け、羅針盤となるよう願ってやまない。
世古一穂・土田 修
上記内容は本書刊行時のものです。