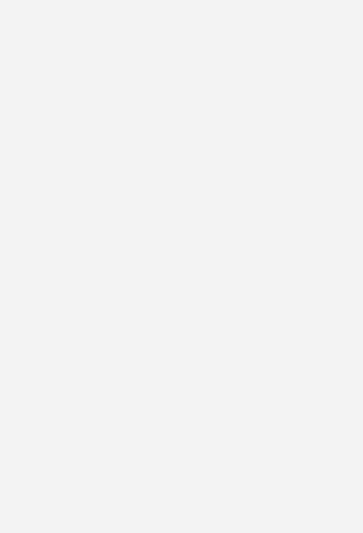書店員向け情報 HELP
出版者情報
書店注文情報
在庫ステータス
取引情報
障害者と笑い
障害をめぐるコミュニケーションを拓く
- 出版社在庫情報
- 在庫あり
- 初版年月日
- 2018年8月
- 書店発売日
- 2018年8月31日
- 登録日
- 2018年8月17日
- 最終更新日
- 2018年9月7日
書評掲載情報
| 2018-11-10 |
朝日新聞
朝刊 評者: 寺尾紗穂(音楽家、エッセイスト) |
| MORE | |
| LESS | |
紹介
なぜ笑ってはいけないのか?
「身障者」と「笑い」はもっとも結びつきにくいテーマです。「身障者を笑ってはいけない」「身障者が人を笑わせることはできない」などは社会的「良識」となって我々の身に染みこんでいます。しかし著者は、そこに根拠はあるのかと問い、笑いをめぐって障害者がいかなる視線のなかにおかれてきたかを主にメディア表象のなかに探ろうとします。従来の身障者像に乗っかって感動を売り物にする「感動ポルノ」が多いなか、新しい可能性を予感させる『バリバラ』(Eテレ)の意欲的試みなどを取り上げて、その企図と思想的意味を解明します。「笑い」という破壊的な力を手がかりに、既存の障害者イメージを瓦解させ、「差別する者─される者」の構図に大転換を迫る意欲的試みといえましょう。
目次
障害者と笑い 目次
はじめに
第一章 笑いの役割
第二章 障害者と笑いの関係
第一節 笑いの対象としての障害者
第二節 障害者と笑いの乖離
第三節 笑いのパフォーマーとしての障害者
第三章 現代社会におけるバラエティ番組の位置
第四章 『バリバラ』における障害者と笑い
第一節 『バリバラ』の企図
第二節 『きらっといきる』から『バリバラ』へ
第三節 「自己改革」という視点
第五章 障害者パフォーマンスと現代的コミュニケーション
第一節 演じる/演じられる身体の虚構性
第二節 「良きオーディエンス」を演じるということ
第三節 「良きコミュニケーション」を想定するということ
おわりに
注
引用・参考文献
事項索引
前書きなど
障害者と笑い はじめに
はじめに
メディアをつうじて障害者がいかに描写されてきたのかという問題は、社会において障害者がいかなる存在として捉えられてきたのかという問題と表裏一体の関係にある。そして、社会において障害者がいかなる存在として捉えられてきたのかという問題は、障害がいかなるものとして定義づけられてきたのかという問題と密接な関係にある。「障害者表象」と「障害者観」と「障害認識((1))」は、いつの時代にも連動しながら変遷してきた。だからこそ、メディアにおける障害者表象を考察することは、同時に、社会における障害者や障害の位置づけを明らかにすることにつながる。
昨今の障害者表象は、多くの水準でアンヴィヴァレントな状況に置かれている。たとえば、テレビや映画といったポピュラーなメディア領域における障害者の描かれ方は、もはやあからさまな差別や偏見とは無縁のようにみえる。しかし、それが「がんばる障害者」「純粋無垢な障害者」といった一方向的なステレオタイプであるという意味では、昨今の障害者表象もまた、ある種の差別や偏見をもたらしている。
旧来より障害者は表象の対象であり続けてきたが、それは本書で詳述されるように、テレビをはじめとするメディアによって、障害者が都合の良い消費コンテンツに転換しやすい素材として扱われてきた、という消極的・限定的な意味合いによるところが大きい。だからといって、障害者がメディアに出演する機会が多いわけではない。そのなかでも障害者の進出がひときわ少ないのが、コメディ映画やバラエティ番組のような「笑い」という要素を包摂するジャンルである。少なくとも日本では、コメディ映画に障害者の主人公が登場したり、バラエティ番組に障害者の芸人が出演したりする場面を見かけることはほとんどない。ましてや、障害者が「障害者である」ということに言及せずに、あるいは障害というテーマとは無関係な文脈において、そのような作品や番組に出演する機会は非常に限られている。
現代の日本社会において、そうした文化的土壌が形成された要因には、一般的に「障害者である」ことと「芸人やコメディ俳優である」ことが両立不可能なものと理解される傾向があり、また「障害」と「笑い」という両要素が結びつけて想起される機会がほとんどない、という点があげられる。簡単にいってしまえば、障害者が登場すると「笑えない」と判断されてしまうわけである。そして先述のように、「障害者表象」と「障害者観」と「障害認識」が綿密に連動する社会において、そのような感覚はメディア表象の水準のみに差し向けられるものではなく、私たちの日常生活に浸透しているものだともいえよう。
それでは、なぜ「障害者」と「笑い」を結びつけることが相応しくないと判断されたり、ときにはタブー視され、忌避の対象として扱われたりするのだろうか。比較的容易に想像できるのは、いわゆる「感動ドラマ」において描出されるような「がんばる障害者」や「純粋無垢な障害者」に見慣れてしまった視聴者にとって、「おもしろい障害者」や「笑いをとる障害者」という障害者像が馴染みにくくなってしまっている、という点である。しかしそれ以上に、多くの人々が子どもの頃から「障害者を笑ってはいけない」と教育されたり、その規範を内面化したりしながら成長してきたことが、そこには少なからず関与していると考えられる。そういった社会的認識が身体化されることにより、「なぜ障害者を笑ってはいけないのか」という問いは後景化し、健常者のほとんどは「いかなる状況においても障害者を笑うなど、とんでもないことである」と反射的に判断してしまうようになる。ようするに、はじめは「障害者を笑う」という行為のみを対象としていたタブー意識が、次第に「障害者が笑いに関与する」という事象へと拡張され、より広範な問題においても適用されていく経緯があったと推察されるのである。その結果として現代社会は、「障害者を笑うこと」と「障害者が笑うこと」と「障害者と笑うこと」を混同し、障害者と笑いの関係性に言及することの一切を忌避するという、異様ともいえる風潮を招来してきたのではないだろうか。
ともあれ上記のプロセスが意識化されることは稀であるにせよ、多くの人々は「障害者はすばらしい」「障害者は尊い」といった態度を(少なくとも表面的、あるいは公けには)とるほうが妥当であると捉えているようである。それは、「障害者福祉」や「障害者共生」といったスローガンがもはや目新しいものではなくなった現代社会において、障害者に対して調和的な立場をとるほうが「いい人」という外面を保てるからであり、なによりも、そうしておくほうが無難であったり楽であったりするからである。そういった態度とも結びついて、多くの視聴者が「がんばる障害者」を見て涙を流すように、障害者表象は健常者が感情に身をまかせることの心地よさを叶えるための一つの手段として消費されていると把捉してみることができるだろう。
このように、一度でも情緒的な領域に引き込まれてしまった事象は笑いと縁遠いものになりやすい。哲学者のアンリ・ベルクソンは『笑い』のなかで、感情に働きかけるような事柄がいかに笑いに転じにくいかを指摘している。
笑いは情緒とは相容れない。どんなのでもよいが軽微な或る欠点を私のために描いてくれたまえ。もし諸君が私の同感、あるいは恐怖、あるいは憐憫の情を動かすような具合にしてそれを示されたら、何としても詮方ない次第で、私はもはやそれを笑うことができない。これに反して、根深いそして一般的に言えばむしずの走るような悪徳を選んでみたまえ。もし適切な技巧によって、諸君がまずそれを私に心を動かされないものにすることに成功されたなら、諸君はそれを滑稽化することができるというものだ。そうすると、悪徳が滑稽になると言うのではない。そうした上で、それが滑稽になりうると言うのである。私の心を動かしてはならぬ、そういうことが、それだけではもちろん十分だとは言えないが、ほんとうに必要な唯一の条件である。(一二九頁)
ベルクソンは『笑い』における別の箇所で、情緒を働かせなければ「傴(せむし)僂(せむし)」((2))をも笑うことができると述べている。しかし、もはや現代社会においては事情が少し違っている。仮に私たちが「傴僂」に対して情緒を働かせなかったとしても、そこに「障害」や「病」といったフレームが介在するかぎりは、それが「安易に笑わないほうが(さらにいえば、関わらないほうが)妥当である」と感情づけられる可能性は大きい。その意味で、何かを「笑う」という行為と同じように、何かを「笑わない」(「笑えない」)という行為は、その人やその社会の価値観を反映しているのである。
何かを「笑う」ということと、何かを「笑えない」ということは、表裏一体の問題であるにもかかわらず、「なぜ笑えないのか」を私たちが問うことはあまりない。「笑う」という行為をめぐっては学問的にも従来さまざまな議論が展開されてきた。しかしアカデミックな言説においては、「笑いがどのような条件下で発生するのか」が焦点化されることはあっても、逆に「なぜある特定の状況において、人々は笑うことを躊躇したり、笑うことが不可能になったりするのか」が焦点化されることはほとんどない。だが、「笑う」と「笑えない」が表裏一体の問題だからといって、笑いが生じる条件をただ単に反転させれば、「笑えない」という状態について考えたことになるのかといえば、決してそうではない。なぜならば「笑えない」という事実は、笑いが生じるための条件の不足によって発生するわけではなく、一定の取捨選択や価値判断のうえで実行された行為だからである。
「笑う」という行為は、社会的に黙認され共有された境界の侵犯―たとえば、普通と違うものや過度に強調されたもの―に向けられるということが学問的には頻繁に指摘されているが、それは「笑えない」という状況にも該当するのではないか。だとすれば、「笑う」と「笑えない」は決して対の関係にあるわけではない。「笑える」ものがある一線を越えると、途端に「笑えない」ものへと転換しうることもある。そこには、社会的なタブー化のプロセスが介在している。
本書の試みは、テレビなどのメディアにおける障害者表象に向けられた視線の変遷を、「笑い」という視座から読み解こうと試みるものである。一般的な感覚でいえば、障害者表象をめぐる問題と「笑い」をめぐる問題を関連づけて論じることは、ややもすると、意外な組合わせのように感じられるかもしれない。しかし、笑いが社会的なコードや人々の認識を前提に生起しうる事象であるならば、そのような視点は、障害者表象を社会的な水準から考察するための一助となる。障害者と笑いの関係を紐解いていくことは、その背景に存在する社会構造や政治性の問題を照射することにもなるだろう。
以下では、あらかじめ本書の構成について予告的に概観しておきたい。まず第一章では、理論的な視座を導入しながら、笑いの社会的な役割を提示する。ここでは、笑いにはある種の批判性が付随することを指摘し、笑いが社会的なコードや権力構造を前提として成立する事象であることを明らかにする。
つづく第二章では、障害者と笑いが歴史的変遷のなかで、どのような関係性に置かれてきたのかを考察の俎上に載せる。かつて「笑いの対象」とされてきた障害者が、次第に「笑い」という営為と切り離されていくようになる経緯を時系列的に整理していく。またそのような状況ふまえたうえで、「パフォーマーとしての障害者」という新たな位置づけの意義についても論及することになる。
第三章では、次章における議論の展開―障害者によるバラエティ番組の事例分析―を見据えて、その前段階として、そもそもバラエティ番組の現代的な特性とは何かを考えていく。また、そこでの笑いが「視聴者の読み」や「社会的な企図」とは分断された記号として消費されている点を抽出する。
さらに第四章では、障害者と笑いの関係性を問い直すための画期的な試みといえる事例―NHKが放送する障害者によるバラエティ番組『バリバラ』―を取り上げて分析する。この番組が置かれてきた変遷プロセスに着眼しながら、そこに見出せる立ち位置の特異性や、そこで提起される笑いの社会的な意味を探っていく。
最後の第五章では、「コミュニケーション」という視点を新たに導入しながら、『バリバラ』における障害者パフォーマンスと、それを視聴するという行為の意味について考察する。パフォーマンスを見るという行為が「良きオーディエンスを想定する」という態度や、「良きコミュニケーションを想定する」という振舞いのうえに遂行されることに留意し、障害者のお笑いが視聴行為の実践のなかで意味づけられていくことを明らかにする。
繰り返しになるが、本書が「障害者と笑い」というテーマを扱うのは、笑いという営為をめぐって障害者がいかなる抑圧に晒されてきたのかを記述することによって、障害者に対する社会の偏見やステレオタイプを明らかにするためであり、当然のことながら「障害者を笑いの対象にする」という旧来的な構図を肯定するためではない。既述のように、現代の社会が「障害者を笑うこと」を忌避することの延長線上で障害者と笑いの関係に言及することまでタブー視し、障害者が笑いと積極的にかかわろうとする機会を奪ってきた状況を考えれば、本書が扱うような「障害者と笑い」というテーマを論じること自体が、そのような状況に一石を投じる試みの一端になるかもしれない。
私たちが何かを笑うということは、単なる感情の発散にすぎないのだろうか。あるいは、私たちがメディア表象を受容するということは、単なる娯楽的な営為にすぎないのだろうか。たとえ意識することが少ないにせよ、もしかしたらそこには見えない力―知らず知らずのうちに、何かを「笑える/笑いえない」と判断したり、ステレオタイプ表象を妥当なものとして受け入れてしまう感覚が、介在しているかもしれない。ふと思い浮かぶこうした疑念に立ち止まり、それに向き合ってみることこそが、本書の目指すところである。
上記内容は本書刊行時のものです。