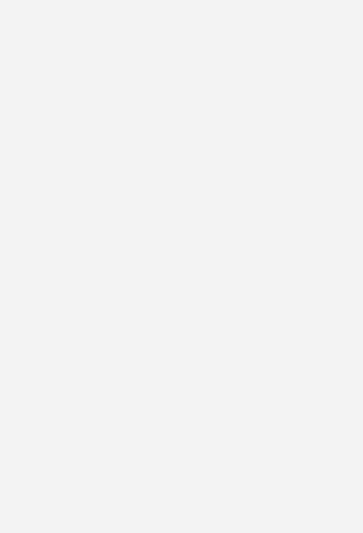書店員向け情報 HELP
出版者情報
書店注文情報
在庫ステータス
取引情報
村上陽一郎の科学論
批判と応答
- 出版社在庫情報
- 在庫あり
- 初版年月日
- 2016年12月
- 書店発売日
- 2016年12月27日
- 登録日
- 2016年12月1日
- 最終更新日
- 2017年12月12日
紹介
◆3・11後、科学論は展望を開けるか?
村上陽一郎は『西欧近代科学』『近代科学と聖俗革命』(小社刊)などを始発に、「聖俗革命」「科学史の逆遠近法」などの魅力的な概念を提案し、科学史・科学哲学に新風を吹き込みました。その後も『新しい科学論』『科学者とは何か』『安全学』などのベストセラーを連発し、多くの一般読者も得ました。本書はその謦咳に接した気鋭の論者たちが、村上科学論とは何だったのか、ポスト3・11の世界にどのような意味を持つのかという観点から、その理論を冷静かつ厳しく「批判」し、それに村上が、「学問的自伝」をからめながら、真摯に「応答」したものです。そこには、教師と弟子という縦の関係ではなく、同じ道を歩む研究者どうしの、自由で平等な学問的関係が見られます。村上科学論の総決算の書といえましょう。テレビでおなじみの林修先生も、村上の講義に魅せられた一人だそうです。
目次
村上陽一郎の科学論 目次
序文 編者
学問的自伝 村上陽一郎
主要著作紹介 編者
村上科学論への誘い
「正面向き」の科学史は可能か? 野家啓一
科学の発展における連続性と不連続性 橋本毅彦
村上陽一郎における総合科学と安全学 成定 薫
村上科学論への批判
聖俗革命論に「正面向き」に対する 高橋憲一
聖俗革命は革命だったのか――村上「聖俗革命」をイギリス側から見る 小川眞里子
聖俗革命論批判――「科学と宗教」論の可能性 川田 勝(構成・注 加藤茂生)
村上陽一郎の科学史方法論――その「実験」の軌跡 坂野 徹
村上陽一郎の日本科学史――出発点と転回、そして限界 塚原東吾
科学批判としての村上科学論――科学史・科学哲学と「新しい神学」 加藤茂生
支配装置としての科学――哲学・知識構造論 瀨戸一夫
社会構成主義と科学技術社会論 横山輝雄
村上科学論の社会論的転回をめぐって 柿原 泰
村上医療論・生命論の奥義 小松美彦
批判に応えて 村上陽一郎
村上陽一郎 略歴・役職歴
村上陽一郎 主要著作リスト
事項・書名索引
人名索引
装幀―難波園子
前書きなど
村上陽一郎の科学論 序文
科学史・科学哲学という新興の学問に身を投じてから約半世紀、村上陽一郎は、疑いなく、科学をめぐる議論の幅広い領野において、日本のオピニオン・リーダーの一人であり続けてきた。村上は、一九六八年に『日本近代科学の歩み―西欧と日本の接点』、一九七一年に『西欧近代科学―その自然観の歴史と構造』と、日本近代科学と西欧近代科学をそれぞれ広く射程に入れた書物を相次いで書き下ろし、日本における科学論研究の最前線に躍り出た。以降、村上は、科学史と哲学の融合を目指し、それまでもその後も村上一人にしかできないような、分野の垣根を越えて縦横に横断する独自な科学史・科学哲学研究を展開した。七〇年代から八〇年代にかけては、N・R・ハンソンや、P・K・ファイヤアーベントなどの「新科学哲学」を積極的に紹介して、科学論に新風を吹き込むとともに、日本におけるそれまでの常識的な科学観を一変させた。九〇年代以降は、日本のSTS(科学技術社会論)の主唱者として、現代社会における科学・技術をめぐる問題に、新しい視点から切り込み、「安全学」という新たな学問分野を提唱し、主導した。
このように科学論の幅広い分野で、アカデミズムの枠を越えて刺激的な議論を長く展開してきた村上には、従来から、有形無形の多くの共感と、またそれと同時に、批判が寄せられてきた。それらは、表層的な共感・批判から、村上の思想に深く食い込むものまで、広いスペクトラムを構成していようが、村上の思想を批判的に検討しておくことは、これまでの科学論が何であったのかを探り、そして今後の科学論のゆくえを展望するために重要な意味を持つだろう。アカデミズムの内部に留まらず、実践世界での日常性に強く影響を与える場所に位置してきた村上の幅広い議論を検討することを通じて、科学論の来し方行く末に思いを巡らせ、われわれが村上の思索をいかに批判的に継承すべきかを考察し、そしてそれを世に問うことは枢要なことに相違ない。このように考えて本書は企画された。
ここで、村上の科学論の全体を、主要な著書を中心にして、本書の諸論文との関連についても言及しつつ、簡単に紹介しよう。
村上の最初の単著は、先述した、日本科学史論である『日本近代科学の歩み』だが、科学史と哲学の融合を図る村上の方法論が初めて全面的に展開されたのは、本書の野家論文、坂野論文などが扱っている『西欧近代科学』だと言えよう。H・バターフィールドを嚆矢として、西欧近代科学は十七世紀のいわゆる「科学革命」を中心に描かれることが多い。村上のこの本もその点では軌を一にしている。しかし、村上は、科学は客観的・普遍的存在ではなく、西欧近代という文化圏で歴史的に選びとられた一つの文化現象であるとして、科学を相対化する主張を強く打ち出した。近代科学とそれを生み出した文化との関係という点においては、村上は、多くの論考で、科学革命期のヨーロッパの知識人の知識追究の営みには、神の意志の理解という目的があったと論じ、科学とキリスト教が対立していたという誤解を解き、キリスト教文化のなかに科学が生まれたことの持つ様々な特徴を論ずることに努めた。その主張は、『科学・哲学・信仰』(一九七七年)や『新しい科学論―「事実」は理論をたおせるか』(一九七九年)などのコンパクトな書物で明解に論じられ、とりわけ、ときに現在もなお書店で平積みにされている様子が見受けられる後者で広く世に知られることとなった。
本書の高橋論文や川田論文などによると、科学革命期におけるコスモロジーに包括された科学が「神・人間・自然」という三層構造に基づいているのに対し、現在の科学は「人間・自然」という二層構造に基づいている。そのように知識生産の構造から神が脱落する変化を「聖俗革命」と村上が名づけて論じたのが、『近代科学と聖俗革命』(一九七六年)である。聖俗革命論は村上科学史における非常に特徴的な議論なのだが、本書の高橋論文は、それに対し、村上が科学革命期をキリスト教色で染め上げすぎていると厳しく批判している。さらに、小川論文はイギリス科学史の視点から、川田論文は日常的宗教という観点から、それぞれ聖俗革命論に鋭く切り込んでいる。
村上はその後、聖俗革命論をさらに拡大し、ギリシア・ローマ・アラビアの知識が西欧のキリスト教文化と結合し始める十二世紀から、知識がキリスト教から離脱しようとする十八世紀の聖俗革命までを、「大ルネサンス」と称して西欧の知識の歴史を時代区分する、斬新で壮大な歴史観を『新しい科学史の見方』(一九九七年)で提示した。
さらに、村上は『文化としての科学/技術』(二〇〇一年)において、聖俗革命以後に誕生した科学をプロトタイプの科学と名づけ、二十世紀半ばにはネオタイプの科学が生まれたとし、現代まで視野に入れた広いパースペクティヴによる科学史像を示している。本書の柿原論文は、これらの科学の諸タイプについて検討を加え、それぞれに対する村上の評価について問いを立てている。
このような村上科学史におけるビッグ・ピクチャーを、結果として生み出すこととなった村上の歴史記述の方法論は、『科学史の逆遠近法―ルネサンスの再評価』(一九八二年)で論じられている。村上は、歴史を現在の視点から遡及して解釈する勝利者史観も、その逆の行き過ぎをも斥け、歴史を「正面向き」に眺めることを提唱した。そして、その方法を用いて、ルネサンスを古代思想とキリスト教との「錬金術的アマルガメーション」としてとらえている。この村上の歴史記述の方法を徹底することは可能なのか、と歴史哲学の視点から問うているのが本書の野家論文である。また、横山論文は科学哲学の観点から、村上の科学史記述の方法について、村上の科学観の変化と関連させて論じている。そして、坂野論文では、『日本近代科学の歩み』『西欧近代科学』『近代科学と聖俗革命』『科学史の逆遠近法』という四冊の著作を対象として、村上の歴史記述の困難さについて、厳しい指摘が行われている。
科学が、それを包括する文化に依存するという村上の基本的な科学史観が、一九七一年に村上が翻訳したN・R・ハンソンの『科学理論はいかにして生まれるか』や、T・クーンの『科学革命の構造』の科学論に部分的に支えられるものであったことは、論文集『近代科学を超えて』(一九七四年)で告白されている。哲学的色彩が濃い『近代科学を超えて』では、事実が理論に依存すること、さらに科学のパラダイムが特定の文化圏の価値観、世界観にまで遡り得ることが論じられた。その議論は、本書の加藤論文が検討しているように、「新しい神学」という村上の特異な提案へとつながっている。「新しい神学」を含め、信仰と科学の関係については『科学・哲学・信仰』で歴史的かつ哲学的視点から論じられている。
村上は、科学と、文化や信仰といった比較的マクロな視点から見た文脈との関係だけでなく、よりミクロな人間の日常性の文脈と科学の文脈との関係についても、特に日常言語と理論言語の相違に注意を払いつつ『科学と日常性の文脈』(一九七九年)で論じている。本書の瀨戸論文は、主に『科学と日常性の文脈』の検討を通じて、日常的な知識と科学的な知識の関係を含む村上の知識構造モデルについて論じており、知識論として高いオリジナリティーを誇っている。
過去を現在の規準で裁断せず、過去は過去の文脈において理解するという村上科学史の方法論は、「理論の共約不可能性」という科学哲学のテーゼと共通する部分がある。科学理論が文脈に依存し、それぞれの理論が共約不可能であるならば、理論変化はいかにして起こるのか。一九七〇年代の終わりから、村上の考察には理論変化への関心が色濃く現れてくる。その取り組みの結果が『科学と日常性の文脈』、『科学のダイナミックス―理論転換の新しいモデル』(一九八〇年)、論文集『歴史としての科学』(一九八三年)に結実している。本書の橋本論文は、「科学理論」よりもむしろ「科学活動」に光をあてる最新の科学論の観点から、『歴史としての科学』に収録された「理論の共約不可能性」に関する論文を批判的に論じている。ほぼ同時期、村上は『方法への挑戦―科学的創造と知のアナーキズム』(一九八一年)、『自由人のための知―科学論の解体へ』(一九八二年)など、科学哲学者ファイヤアーベントのラディカルな相対主義的科学論を日本に紹介し、日本における「新科学哲学」の流行を生み出した。
一九八〇年代後半から九〇年代にかけて、村上の論考には医療論や生命論が増加する。『生と死への眼差し』(一九九三年)、日本の近代医療史である『医療―高齢社会に向かって』(一九九六年)、『生命を語る視座―先端医療が問いかけること』(二〇〇二年)などが医療・生命論の主な著書である。本書でしばしば村上が言及しているように、基礎医学研究者を父に持つ村上は医学に興味を持っていた。本書の小松論文は、村上の医療・生命論に敬意を払いつつ、村上の人間観・存在観にまで及ぶ考察を深く掘り進めている。
また、一九九〇年代以降、村上は科学・技術と社会の関係に関する考察へと傾斜を強めていく。その変化については、本書の横山論文と柿原論文で分析が行われている。著書としては、同年に出された『文明のなかの科学』(一九九四年)、『科学者とは何か』(一九九四年)が充実した好著である。前者はこれまでの村上科学史論を整理した上で、文明論にまで議論を及ばせており、「(機能的)寛容」という重要な概念も提出されている。『科学者とは何か』では科学者の行動様式が科学社会学の視角から分析され、科学者が科学者共同体の外部に対して責任をとることの重要性が論じられている。本書の塚原論文は、上記の二作に対し、社会思想的観点から、愛情を込めた批判を行っている。
さらに、村上は、一九九八年に日本で行われたSTS国際会議の組織委員長を務めるなど、日本のSTSの成長を支えた。そして、『安全学』(一九九八年)、『科学・技術と社会―文・理を越える新しい科学・技術論』(一九九九年)、『科学の現在を問う』(二〇〇〇年)、『安全学の現在』(二〇〇三年)、『安全と安心の科学』(二〇〇五年)など科学技術倫理や科学・技術と社会に関わる書籍を相次いで著した。また、政府の諮問委員会などの要職も歴任した。本書の成定論文は、村上の年来の主張ならびに『安全学』を高く評価した上で、村上の原子力発電に関する言説に鋭い批判の矢を放っている。
本書は、P・A・シルプ編の『生きている哲学者』シリーズ(Library of Living Philosophers,一九四一年─ )、および、野家啓一編『哲学の迷路―大森哲学 批判と応答』(産業図書、一九八四年)を参考にして、村上の学問的自伝、村上への批判論文、村上の応答、という構成をとっている。村上への批判論文は、ややエッセイ風で読みやすい「村上科学論への誘い」の三本と、学術論文形式の一〇本からなる。それぞれの内容の重複を厳密に排除することはせず、全体としてなるべく村上科学論を幅広くカバーするよう意図した。とはいえ、じゅうぶん扱えなかった領域も残されている。
本書が扱う範囲の説明と、それに関連する、本書の成立の経緯について述べておく。そもそも本書は、村上の学生だった柿原泰、加藤茂生、川田勝(イニシャルが全員Kなので、3Kと自称していた)によって、一九九〇年代後半に構想された。一九九〇年代半ばに、科学史を専攻する大学院生だった三人は、村上の新著の合評会を何度か企画し、村上の胸を借りながら、科学史・科学論における議論の活性化に繋げようとし、また村上が一九九五年に東京大学を退職する機会に、やや大きめの合評会を主催したことを契機にして、本書を構想した。その当時、まだ日本のSTSは草創期であり、村上の科学・技術と社会に関する考察にもその後の新たな展開が予想されたため、本書ではSTS関連の著作は中心的にはとりあげないこととした。村上に対して建設的かつ徹底した批判を行うため、執筆者の選定に際しては、村上と非常に近い人物はあえて避けるように配慮し、結果として本書の陣容に落ち着いた。かつて村上の学生だったことがある執筆者も多いが、学問的議論を行うマナーに則り、あえて「村上先生」と敬称をつけて記すことは避けることとした。
しかし、村上の学問を最も強く継承しており、企画の中心であった川田が一九九九年に不慮の病を得て、半身不随で寝たきりになるなどのアクシデントに見舞われ、企画の実現には長い時間がかかることとなった。今初めて企画を立てるとしたら、本書の扱う範囲も違うものになっただろうが、編者の力不足で、企画の大幅な修正はかなわなかった。最終的に、二〇〇八年三月に行った村上の国際基督教大学退職を記念したシンポジウムの記録を基礎として、本書は構成されることとなった。ただ、残念ながら、事情により、シンポジウムでお話しいただいた方全員の御論考を本書に掲載するには至らなかった。
遅々として編集作業が進まない編者に、愛想を尽かさず、長年辛抱強くつきあっていただいた各執筆者には、心底感謝している。この企画を新曜社に持ち込んだとき、「ぜひ当社で出版しましょう」と、まだ学生だった我々を励ましてくださった元社長の堀江洪氏は残念ながら鬼籍に入られてしまったが、同社編集部の渦岡謙一氏と髙橋直樹氏は、実務に不慣れな編者を大いに助けてくださった。心からお礼を申し上げたい。そしてなにより、自らへの批判が意図される書物の企画を、大きな心で受け止めて、当初から全面的に協力していただいた村上には、感謝の言葉も無い。
二〇一四年一月十三日に川田が亡くなったことは、加藤、柿原にとって、半身がもがれたような苦痛であり続けている。川田の生前に本書を完成できなかったことが強く悔やまれる。本書を、天の、川田勝に捧げたい。
二〇一六年十月
編者
上記内容は本書刊行時のものです。